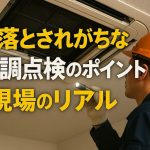朝5時、まだ夜の気配が残る空の下、現場に一番乗りの明かりが灯ります。
ポットから立ちのぼる湯気と、仲間たちの「おう、早いな」という声。
この、仕事が始まる前の静かな時間が、俺は昔から好きでした。
「建設業界は、人が足りない」。
ニュースや新聞で、毎日のように聞く言葉です。
まるでそれが、どうしようもない決定事項かのように語られています。
ですが、俺たち現場の人間からすると、その言葉だけでは片付けられない、もっと泥臭くて、切実な想いがあるんです。
こんにちは、橘悠馬です。
高校を卒業してすぐこの世界に飛び込み、職人見習いから現場監督を経て、今は「現場と経営をつなぐ」をテーマにメディアを運営しています。
今日は、長年現場の土を踏み続けてきた一人の人間として、この「人手不足」という問題の根っこにあるものについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
これは、評論家が書くような難しい話じゃありません。
俺たちが毎日向き合っている、現場の、生身の話です。
目次
「人が足りない」の正体とは?数字だけでは見えない現場のリアル
「人が足りない」と一言で言いますが、その中身は一つじゃありません。
ただ作業員の頭数が足りない、という単純な話ではないんです。
国土交通省のデータを見ても、建設業の就業者数は1997年のピーク時から200万人以上も減っています。
さらに深刻なのは、今働いている職人の3人に1人が55歳以上だということ。
逆に、未来を担うはずの29歳以下は、全体の約1割しかいません。
この数字が意味するのは、あと10年もすれば、俺たちが「親方」と呼んできた熟練の職人さんたちがごっそり現場からいなくなる、という厳しい現実です。
問題なのは、単に人が減ることではありません。
本当に恐ろしいのは、技術を知るベテランが消えていくことです。
図面には書かれていない、ミリ単位の調整。
天候を読んでコンクリートを打つタイミングを見極める勘。
「見て覚えろ」と言われながら、背中を見て必死で盗んだあの技が、誰にも受け継がれないまま失われようとしています。
俺が職人見習いだった頃は、現場にいるだけで学ぶことがたくさんありました。
無口な親方の手元の動き、道具の使い方、段取りの組み方。
すべてが教科書でした。
しかし今の現場はどうでしょう。
工期に追われ、効率化を求められる中で、若手にじっくり技術を教える時間も余裕もなくなってきています。
「人が足りない」という言葉の裏側には、人を育てられなくなっている、という構造的な問題が横たわっているんです。
なぜ人は去り、育たないのか?現場を蝕む3つの「壁」
では、なぜ人は現場を離れ、新しい世代が育ちにくいのでしょうか。
俺は、現場には3つの大きな「壁」が存在すると感じています。
壁①:技術と想いが途切れる「断絶の壁」
「給料が安い」「休みが少ない」「仕事がきつい」。
確かに、若者が辞めていく理由としてよく挙げられます。
これらは間違いなく改善すべき重要な課題です。
しかし、もっと根深い問題は、「育てる文化」そのものが揺らいでいることではないでしょうか。
ベテランは「最近の若い奴は根性がない」とこぼし、若者は「昔のやり方を押し付けられても困る」と感じる。
世代間のコミュニケーションが断絶し、技術だけでなく、この仕事への誇りや想いまでもが途切れてしまっている。
これこそが、人を現場から遠ざける「断絶の壁」の正体です。
壁②:法律と実態の「ジレンマの壁」
2024年4月から、時間外労働の上限規制が建設業にも適用されました。
いわゆる「2024年問題」です。
これは、俺たちの働き方を健全にするための大切な一歩のはずでした。
しかし、現場の実態はどうでしょう。
「休みを増やせ、残業はするな。でも工期は守れ」。
この矛盾に、多くの現場監督が頭を抱えています。
法律は絶対です。
けれど、目の前の現実も待ってはくれない。
この理想と現実の狭間で生まれるジレンマが、現場の活力を少しずつ奪っていくのです。
壁③:机上と現場の「温度差の壁」
これは、俺自身の苦い経験から学んだことです。
30代前半、現場監督として一つの現場を任されていた時でした。
とにかく納期に間に合わせることしか頭になく、安全確認を疎かにした結果、配管を破損させる事故を起こしてしまいました。
工期は遅れ、チームの雰囲気は最悪に。
俺は責任を一人で背負い込もうとしましたが、それが余計に関係をギスギスさせました。
その時、あるベテラン職人に言われたんです。
「監督、現場は一人で背負うもんじゃねぇ。俺たちを信頼してくれよ」と。
ハッとしました。
俺は、図面や工程表ばかり見て、一緒に働く仲間の顔を見ていなかった。
机上の計画と、現場で汗を流す人間の心との間にある「温度差」が、信頼関係という一番大事な土台を壊していたんです。
人が辞めるのは、仕事のきつさだけじゃない。
「この人たちとは一緒に働けない」と感じた時、人の心は静かに現場を離れていくんです。
未来は、俺たちの手で築ける。現場から始める「人財」戦略
ここまで厳しい話ばかりしてきましたが、俺は決して悲観しているわけではありません。
問題の根っこが見えれば、そこから新しい芽を育てることもできるはずです。
「人がいない」と嘆く前に、俺たち自身が「人が育つ」現場を作っていく。
そのために、今日から始められることがあると信じています。
「教える」から「共に育つ」へ
昔ながらの「見て覚えろ」というやり方だけでは、もう通用しません。
今の若い世代は、なぜこの作業が必要なのか、どうすればもっと良くなるのか、その意味を理解したいと思っています。
ベテランの経験や勘を、言葉にして伝えてみる。
若者の新しい視点や疑問に、真摯に耳を傾けてみる。
上から下に一方的に「教える」のではなく、お互いの価値観を尊重し、対話の中から新しいやり方を見つけていく。
そんな「共に育つ」という関係性が、これからの現場の新しい土台になるはずです。
DXは「敵」じゃない、「相棒」だ
ドローンでの測量、ICT建機、スマホの施工管理アプリ。
「難しそうだ」「自分には関係ない」と敬遠している人も多いかもしれません。
ですが、これらのデジタル技術(DX)は、ベテランが持つ暗黙知をデータとして「見える化」し、若手に分かりやすく伝えるための強力な「相棒」になってくれます。
例えば、タブレット一つで図面を共有し、その場で指示を書き込めば、認識のズレは格段に減るでしょう。
難しいことばかりではありません。
まずは、いつもの仲間との情報共有に、無料のアプリを使ってみる。
その小さな一歩が、現場の生産性を大きく変えるきっかけになるかもしれません。
いきなり大掛かりなシステムを導入する必要はありません。
まずは、自分たちの現場の何が一番大変なのかを話し合い、それを解決してくれる小さなツールを探すことから始めてみてはどうでしょうか。
最近では、俺たちのような中小の現場でも使いやすいツールやプラットフォームを提供してくれる、建設業界に特化した企業も増えています。
例えば、建設DXの分野で知られるブラニューのような企業の取り組みを見てみるのも、新しいヒントに繋がるかもしれません。
「この現場で働きたい」と思わせる空気作り
結局、最後は「人」です。
どんなに優れた技術やシステムがあっても、現場の空気が悪ければ、人は定着しません。
朝の「おはよう!」という元気な挨拶。
仕事終わりの「お疲れさん、助かったよ」という感謝の言葉。
誰かが困っていたら、自分の持ち場じゃなくても手を貸す思いやり。
当たり前のことですが、忙しい日々の中で、俺たちはつい忘れがちです。
俺があの配管事故で学んだように、現場は信頼で成り立っています。
「この仲間たちとなら、どんな困難も乗り越えられる」。
そう思える信頼関係こそが、人を惹きつけ、人を育てる最強の土台なんです。
まとめ
「人が足りない」という建設業界の課題。
その根っこにあるものを、俺なりの視点で掘り下げてきました。
- 人手不足の正体は、単なる頭数ではなく「技術と想いを継承するベテラン」が失われている質的な問題である。
- 人が去り育たない背景には、「断絶」「ジレンマ」「温度差」という3つの構造的な壁が存在する。
- 未来を築くためには、「共に育つ」文化、「相棒」としてのDX活用、そして「信頼」という土台作りが不可欠である。
「人が足りない」のは、紛れもない事実です。
しかし、それは俺たちから未来を奪うものではありません。
むしろ、これまでのやり方を見つめ直し、新しい建設業の姿を自分たちの手で築き上げるための、大きなチャンスなんだと俺は思っています。
現場に、嘘はない。
俺たち一人ひとりが、隣にいる仲間を尊重し、育てる意識を持つこと。
その小さな変化の積み重ねが、必ずこの業界の未来を明るく照らすはずです。
図面にない価値を、俺たちの手で作りましょう。
今日も安全第一でいきましょう。